
難しく言い回しの似た用語の並ぶ「社会的養護」は、統計データも沢山出題され勉強法に困りますよね。
私も最後まで試験対策が適切かモヤモヤしていました。
お伝えしたいことが沢山あるため前編・後編に分けご紹介します。当記事は「後編」です。
この記事では保育士試験科目「社会的養護」の勉強法についてトピック毎に解説します。
この科目を構成する3本柱は社会的養護の「歴史」「現在の体系理解」「統計データの把握」

社会的養護は保育原理、教育原理や子ども家庭福祉とも出題内容が重複しているせいか論点がぼやけがちでカテゴリーに分けて勉強するのが難しいように感じました。
ここでは3つの論点に分けて社会的養護の全体像把握からはじめます。
この科目の全体像を眺めると、大まかに3つの論点で構成されています。
【3つの論点】
1.社会的養護の歴史
2.社会的養護の現在の体系理解
3.「社会的養護の現状について」等の統計データの傾向把握
「歴史」については「理解」というより事実を「覚える」内容ですので、早期より暗記対策を進めましょう◎
勉強の進め方がモヤモヤしがちな論点2.3ついては、内容理解に努めたトピックや使用する統計データについて紹介します。
論点1.歴史と、論点2現在の体系理解については、社会的養護の勉強法【前編】にてご紹介!
下記リンクよりぜひ☆
論点3:よくでる厄介者!「統計データの把握」は過去と最新版とを比較しよう!

おそらく社会的養護で一番苦手な理由がこの「統計データの把握」なのではないでしょうか。
数字に弱い私は「社会的養護の現状について」の表を見て、直前にまたやろう!と閉じたのを覚えています。
もう1つ頻出の統計データが「児童養護施設入所児童等調査」ですね。
こちらも厚生労働省のPDFを見て、量の膨大さに×をすぐ押した記憶が。。。
大切なのは「数字の規模感を把握」と「過去との比較による傾向把握」の2点です★
「社会的養護の現状について」は毎年同じフォーマット!ガンガン比較と傾向把握を進めよう!
「社会的養護の現状について」は毎年更新されており、受験年度での最新版がどの年度のデータになるのかをまず確認が必要です。
その上で、1つ前の年度を過去データとしてインターネット検索し取得しましょう。
参考までに下記リンクが「社会的養護の現状について平成28年度版」です。
「社会的養護の現状について」の分析観点と着眼点
年度にかかわらずほぼ同じフォーマットの統計データですので、下記【着目点・分析観点】を参考に過去と最新版とを見比べ傾向を把握しましょう。
【着目点・分析観点】 ・冒頭の対象児童数と共に各児童数・各施設数の増減に注目 →急激に増減?緩やかに増減?の把握 ・施設数の増減では「家庭養護」「施設養護」の視点で見てみよう →おそらく施設の小規模化が進んでいるため、施設数にも表れているはず ・各施設の現員数を少ない順(又は多い順)に並べてみよう ・里親も区分ごとに少ない順(又は多い順)に並べてみよう ※現員数と定員数の差も着眼点になります、満員に近いのか空きがあるのかを把握 ・児童数・施設数の数の規模感だけは(2桁?3桁?4桁?)なるべく覚えましょう

ご自身での分析を終え問題演習を行う中で、出題箇所を実際のデータで調べて見返す、その繰り返しで苦手意識は徐々に薄らぎ能動的に取り組めるようになるはずです!
おまけ:「社会的養育の推進に向けて」は10ページまで目を通しておこう
「社会的養育の推進に向けて」は厚生労働省の「新しい社会的養育ビジョン」等を扱う資料です。
どのようにケアすればよいか分からず、ただほうっておく勇気もなく…

まずは「社会的養護の現状について」のデータも掲載されている10ページ目までを目を通すことをおススメします。
私はさらに新しい社会的養育ビジョンの概要や意義など「考え方の骨格」となる文章(下記リンク12-17ページ)辺りが重要なのかなとヤマを張り目を通しておきました。
2大巨頭!「児童養護施設入所児童等調査」も前回値との比較と傾向把握が大事◎

「社会的養護の現状について」と並び頻出の統計データが「児童養護施設入所児童等調査」
この対策も悩まれる方多いのではないでしょうか。
厚労省で公表のPDFは50ページを超える大作ですから、全てを網羅するのは厳しいです。
ある程度出題されそうなやまを張りつつ、比較と傾向把握をはじめましょう!
まずは元データとなる厚労省「児童養護施設入所児童等調査」のデータを取得しましょう。
「児童養護施設入所児童等調査」の表の上の概要説明だけ見ればOK!着目点と分析観点
実際に「児童養護施設入所児童等調査」の中を見ると、各ページ冒頭に概要説明の文章・その下に表が掲載されています。
概要説明が前回調査の数値も併記されており重要ですが、下部の表は正直見なくとも問題ないかと思います。
加えて「児童養護施設入所児童等調査」をご自身で見ていく際の分析観点も、基本的には上記でお伝えの「社会的養護の現状について」と同様です。
【「児童養護施設入所児童等調査」の分析観点】
・割合(%)は前回調査の数値と比較しよう(増加?減少?横ばい? 急激に増えてる?)
・年齢・期間は全体の傾向をみる(低年齢化してる?長期化してる?短期間になってる?)
・最も数値の大きい内容・最も小さい内容を確認しよう
私ならここやる!「児童養護施設入所児童等調査」のヤマ張り箇所一覧リスト◎

さて50ページ超えの「児童養護施設入所児童等調査」のうち、私ならここ勉強する!という独自見解のヤマ張り箇所一覧を作成しました!
「児童養護施設入所児童等調査」の目次ページと照らし合わせながら該当ページをご確認くださいね。
リスト作成にあたり基本的な考えとして「年齢・人数・期間・養護理由は重要」としています。
これに追加し問題演習の出題箇所を見返すことで、だいぶ網羅され対策として十分かと◎
【「児童養護施設入所児童等調査」ヤマ張り箇所一覧】 ◎は重要と思われる箇所 Ⅰ 児童の現在の状況 ◎1 児童の現在の年齢 ◎2 児童の委託(入所)時の年齢 ◎3 児童の委託(在所)期間 5 児童の就学状況 Ⅱ 委託(入所)時の家庭の状況 ◎1 養護問題発生理由 ◎2 児童の被虐待経験の有無、虐待の種類 3 委託(入所)時の保護者の状況 Ⅲ 家族との関係 1 家族との交流関係 2 児童の今後の見通し Ⅳ 里親家庭の状況 ◎1 里親申込みの動機 ◎2 登録期間 Ⅴ 母子生活支援施設入所世帯(母親)の状況 ◎1 児童数 ◎2 入所理由及び在所期間 ◎3 入所時の年齢 ◎4 母子世帯になった理由 Ⅸ 障害児入所施設の児童の状況 ◎2 入所児童の契約、措置の割合 ◎3 入所時の年齢別児童数 ◎4 在所期間別児童数 ◎7 児童の心身の状況 Ⅹ 障害児入所施設の委託(入所)時の家庭の状況 ◎1 養護問題発生理由 ◎2 児童の被虐待経験の有無、虐待の種類
児童虐待の相談件数は最新数値まで調べて増加度合いを把握しよう

児童虐待関連については注目度の高いテーマですので、テキスト記載の児童虐待相談件数だけでなく最新年度の件数まで調べておきましょう。
増加がいつ頃までは緩やか?、いつ頃から急激?など傾向まで把握すると安心です。

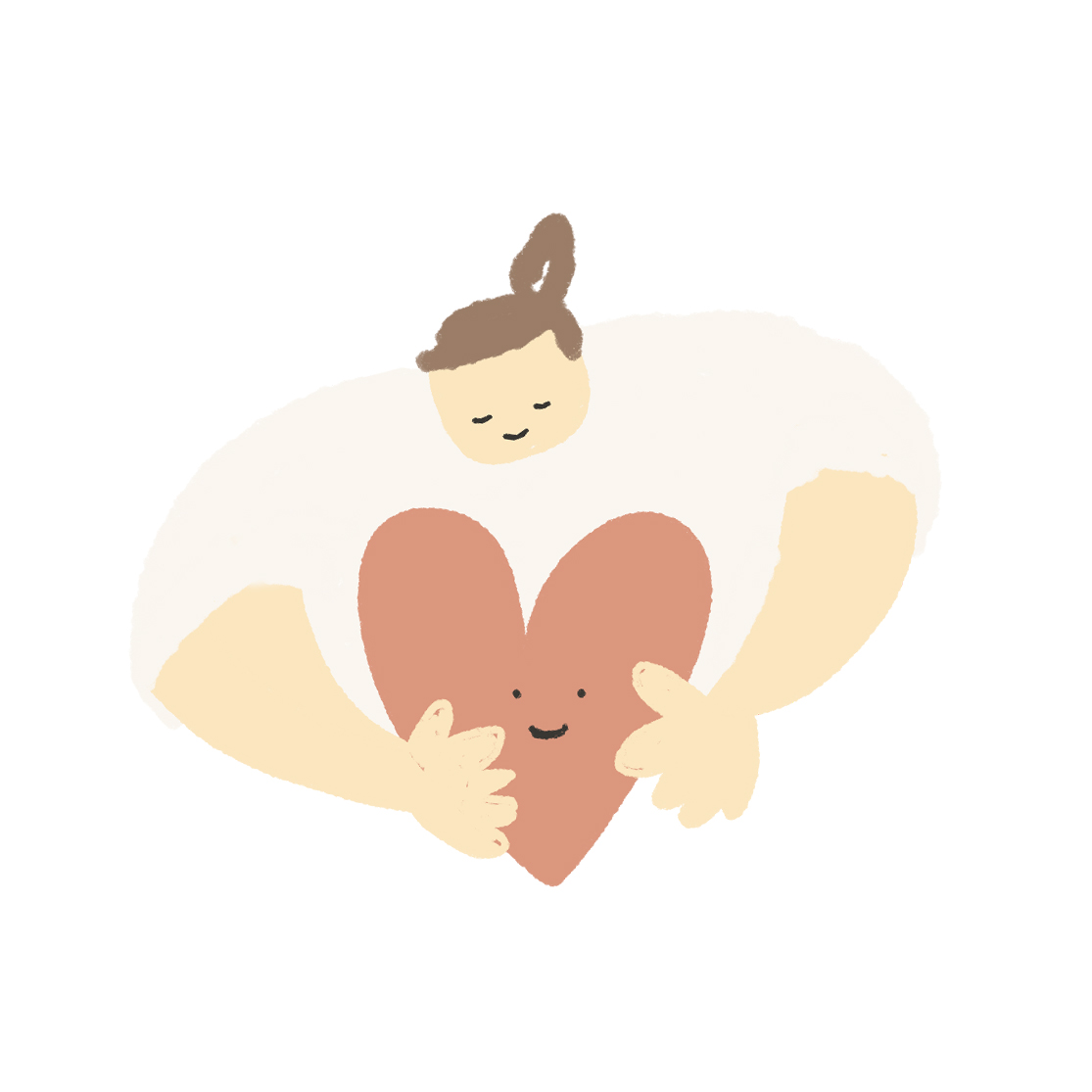



コメント